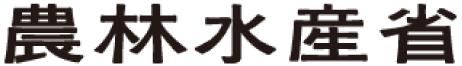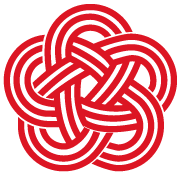
房切り大根(ふさきりだいこん)

熊本県房切り大根(ふさきりだいこん)
分類(大)
農産
分類(小)
その他農産加工品
主な使用食材
大根
※ダウンロード可能な画像を使用する場合は「リンクについて・著作権」をご一読の上、
出典を農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」と明記し、ご利用ください。
なお、画像提供元の記載がある場合は画像提供元も併せてご記載ください。
画像提供元の記載例
【画像提供元の記載がない場合の記載例】
出典:農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」
【画像提供元の記載がある場合の記載例】
出典:農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」
画像提供元:〇〇〇
主な伝承地域
阿蘇地域
食品概要(特徴・種類)
房切り大根は、阿蘇地域で冬の冷たい風を利用してつくられている干しだいこんである。だいこんの収穫時期(11~2月頃)につくられる保存食であり、切り方に特徴がある。一本のだいこんを蛇腹(じゃばら)状に切り込みを入れて切り、竿にかけて干し、調理するときは水で戻し、主に煮物や酢の物、みそ汁の具にも利用する。干してあるため味が染みやすいという特徴があり、パリッという独特の食感は、生のだいこんを使うのとはまた違うおいしさがある。干しだいこんを戻した水にもうま味があるため、捨てずに料理に使うことが多い。
歴史・文化、関連行事
房切り大根という名前はその特徴的な切り方から名付けられ、蛇腹大根、切りかけ大根とも呼ばれている。家の軒下に、白い花のように連ねて干される房切り大根の様子は、阿蘇地域の冬の風物詩である。
長く保存ができるので年間通して使われ、特に冬から春の生野菜が少なくなる時期に重宝した。天日に干すことでうま味や栄養が凝縮され、カルシウムや鉄分、食物繊維が増える。
阿蘇では、お祭りや仏事など冠婚葬祭の時に、季節の野菜や油揚げ、しいたけ、こんにゃくなどを醤油や砂糖で味つける煮しめをつくるが、これには必ず房切り大根を入れる。
製造方法
だいこんを横にして置き、2~3mm幅の輪切りとなるように包丁を入れる。この時切り離さないよう下側を5mmほど残す。だいこんを裏返し、ふたたび2~3mm幅の斜め切りとなるように包丁を入れる。この時も下側を5mmほど残す。このようにだいこんを切り終えると、3倍ほどの長さに蛇腹のように長く伸ばせるようになる。
新鮮な生のだいこんの切りたてはだいこんが硬く伸ばすとちぎれやすいので、ザルなどに入れてやわらかくなるまで置いてから、竿にかけて干す。もしくは収穫しただいこんを数日から1週間ほど干してから切ってもよい。このような蛇腹状にすると、長細くなって干す場所をあまり取らなくてすみ、乾燥も早く進む。1週間ほど干して出来上がる。
保護・継承の取り組み
道の駅や産直市場などで販売されている。
主な食べ方
煮物、酢の物、炒め物、みそ汁などに使う。冠婚葬祭の時の煮しめに必ず入れられる。
アレンジレシピ:房切り大根の煮物
材料
蛇腹大根(切りかけ・房切り)
1本
しいたけ
3枚
人参
1/2本
ねぎ
1/2本
卵
2個
醤油
1/2カップ
砂糖
大さじ1と1/2
油
少々
作り方
蛇腹(切りかけ・房切り)大根:葉をおとし4~5日好天の日に干し、しんなりさせたものを使用する。3mm間隔で7分目までまっすぐに切り目を入れる。切り目を入れたところを下にして斜めに3mm間隔で7分目まで切り目を入れる。 好天の日、並べて干し、柔らかくなったら、竿に干し、乾いたらのばしながら干しあげていく。生の大根の3倍の長さに仕上げる。
しいたけは水でもどし、蛇腹大根はぬるま湯に2~3分浸す。そしてまな板の上に2~3分おいておく。
人参、ねぎ、しいたけを細長めに切る。蛇腹大根の水気を拭き、1cm位に切る。
油を少々入れた鍋に蛇腹大根、しいたけ、人参の順で入れ中火で炒める。
なじんだら少量の水(または酒)を加える。
だいぶしんなりなったところで砂糖、醤油を入れる。
ねぎを入れる。
卵2個をといて入れ、手早く混ぜ合わせてできあがり。