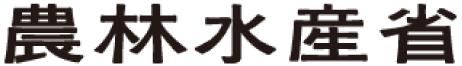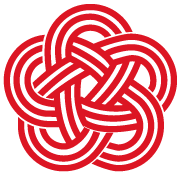
こも豆腐(こもどうふ)

茨城県こも豆腐(こもどうふ)
分類(大)
農産
分類(小)
その他農産加工品
主な使用食材
豆腐
※ダウンロード可能な画像を使用する場合は「リンクについて・著作権」をご一読の上、
出典を農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」と明記し、ご利用ください。
なお、画像提供元の記載がある場合は画像提供元も併せてご記載ください。
画像提供元の記載例
【画像提供元の記載がない場合の記載例】
出典:農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」
【画像提供元の記載がある場合の記載例】
出典:農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」
画像提供元:〇〇〇
主な伝承地域
県内全域
食品概要(特徴・種類)
古くから納豆で有名な茨城県は、作付面積、収穫量とも関東トップクラスの大豆の一大産地である。主に小粒の大豆は納豆に加工され、大粒の大豆は豆腐に加工される。そうした大豆を使った郷土料理のひとつがこも豆腐である。
こも豆腐は、豆腐を納豆のように藁苞(わらずと)や菰(こも)で包み、塩茹でしたもので、藁苞から豆腐を取り出すと、藁の跡が美しい模様を作り出す上に、ほんのりと藁の香りや色が豆腐に移り、それがこも豆腐ならではの素朴な味わいにつながっている。
茨城県内では、藁で包んだ食品を「つと(苞)」と呼ぶことから、つと豆腐とも呼ばれている。茨城県の他にも、福島県や群馬県、岐阜県の一部の地域でも作られている。福島県では、藁苞や菰の代わりに豆腐を竹づと(竹すだれ)に入れて作られている。
歴史・文化、関連行事
豆腐は今から2,000年前、漢の時代に中国で誕生し、その後、奈良時代に遣唐使によって日本にもたらされたと言われている。お寺の精進料理に重宝されたものがやがて庶民の間にも広まり、江戸時代にはすでに豆腐屋が繁盛していたという。
肉が簡単に手に入らなかった時代は、豆腐はタンパク質が得られる大切な食材であったが、あまり日持ちをしないことから、藁に豆腐を詰めて大鍋で塩茹でにして保存性を高めたという、庶民の知恵から生まれた料理だと言われている。
製造方法
水切りした豆腐をほぐしながら藁苞に詰め、藁で巻きながら形を整え、塩を入れた熱湯に入れてしっかりと茹でる。塩茹ですると豆腐が締まっていくので、固くなったら取り出して冷まし、藁苞から外す。最後にだし汁で煮含め、一晩ほど寝かしてから食べる。食べる際は、醤油や味噌を付けて食べるのが一般的である。
こも豆腐に使用されている主な食材は、豆腐、だし汁、砂糖、醤油。また豆腐を藁で包む際ににんじんやごぼうなどを芯にして包む場合もある。
保護・継承の取り組み
茨城町では、茨城大学との連携事業において郷土料理であるつと豆腐(こも豆腐)に着目し、調査・研究を行ってきた。つと豆腐(こも豆腐)にまつわる食文化や歴史を研究するだけでなく、平成28年度には町内の高校生やNPO団体等に連携を広げながら、「茨城町で代々受け継がれてきた食を探るインタビュー調査」および「つと豆腐の試食会と購買意欲等に関するアンケート調査」を実施した。
それらの取り組みの成果としてパンフレット「いばらきまちで暮らす ―郷土料理“つと豆腐”deひとしな」を作成し、茨城町のウェブサイトで公開している。
主な食べ方
正月の料理や法事の際のおもてなし料理として提供されることが多いが、現在では藁が入手しにくいため、一からこも豆腐を作る家庭は減っている。一方、茨城県の特産品として、市販のこも豆腐を購入する観光客は多い。