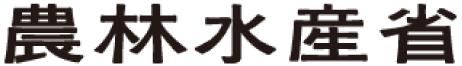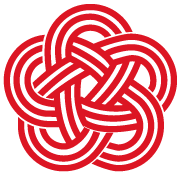
松江和菓子(まつえわがし)

島根県松江和菓子(まつえわがし)
分類(大)
その他
分類(小)
菓子類
※ダウンロード可能な画像を使用する場合は「リンクについて・著作権」をご一読の上、
出典を農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」と明記し、ご利用ください。
なお、画像提供元の記載がある場合は画像提供元も併せてご記載ください。
画像提供元の記載例
【画像提供元の記載がない場合の記載例】
出典:農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」
【画像提供元の記載がある場合の記載例】
出典:農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」
画像提供元:〇〇〇

画像提供元:島根県
この画像はダウンロードできません

画像提供元:島根県
この画像はダウンロードできません

画像提供元:島根県
この画像はダウンロードできません
主な伝承地域
松江市
食品概要(特徴・種類)
400年前に創建された松江城を中心に城下町の風情が色濃く残る松江は、京都、金沢と並ぶ「日本三大菓子処」の一つと言われている。お茶と和菓子の街の礎を築いたのが大名茶人として知られる松江藩七代藩主松平治郷(不昧公)。松江には不昧公が育んだ茶の湯文化が今も生活の中に息づいており、街では多くの茶舗や和菓子の老舗が暖簾を守り続けている。
不昧公の時代に和菓子の文化も育まれ、松江三大銘菓とも言われる「若草」「山川」「菜種の里」、藩主専用で他所売りが禁じられたお留め菓子である「姫小袖」など多くの銘菓が誕生している。
歴史・文化、関連行事
1767年、17歳で松江藩七代目藩主となった松平治郷は、天災等により財政難にあった松江藩を立て直す一方、茶の湯に熱心で、のちに作法やしきたりにとらわれず、もてなしの心を重んじる茶道「不昧流」を完成させた。当時、不昧公が茶会で使った和菓子や茶道具は「不昧公好み」として今も受け継がれている。
当時の茶会に出されていた和菓子は、明治維新以降、一度は姿を消したが、菓子を愛する市民と、和菓子作りに情熱を燃やす職人の熱意によって復活を遂げ、現在も老舗菓子舗によって松江銘菓として守られ続けている。
製造方法
松江三大銘菓に代表される松江の和菓子は、職人が手作りで仕上げている。
「若草」は、柔らかな求肥に薄緑の砂糖と寒梅粉をまぶした和菓子。もち米を石臼で水挽きするという、昔ながらの伝統製法で作られている。「山川」は、紅白の打ちもので、落雁の中でも柔らかく、しっとりした食感を備えている。「菜種の里」は、春の菜の花畑に白い蝶が飛び交う様を表現しており、地元のもち米を製粉した粉(寒梅粉)と、独特な砂糖「しとり」を混ぜ、ふるいに通し、木枠で固めて作れられる。
どれも水の都である松江の自然の移ろいを、繊細な形状と微妙な色合いで表現している。
保護・継承の取り組み
松江では、特別な稽古事や行事としてではなく、住む人たちが自然とお茶を嗜んでいる。そのため、緑茶と、共に食する和菓子の世帯当たり消費額が全国トップクラスであり、まさに「お茶と和菓子のまち」と言える。
それを支えているのが和菓子職人の高い技術力であり、その源にあるのが茶処松江で開催される多くの茶会である。季節ごとに開催される各流派の茶会は、職人の感性や造形美、品の良い味わいを磨く絶好の機会となっている。
また、会社の垣根を超えた和菓子職人の技術研鑽の場として「松江松和会」がある。戦前から各社の工場長たちが集い、技術向上を図るとともに、多くの松江銘菓の復活を実現させてきた。現在も、全国和菓子協会認定の「選・和菓子職」を擁する日本屈指の和菓子技術者集団として、全国菓子博覧会で高い評価を得ると同時に、技能継承と後進育成にも努めている。
不昧公の命日である4月24日と毎月24日は松江市の条例で「茶の湯の日」に定められ、市を挙げて茶の湯文化に親しむ日となっている。
主な食べ方
茶会だけでなく、普段から日常的に抹茶や煎茶と共に嗜まれている。最近は、紅茶やコーヒーと共に味わう人たちも増えている。