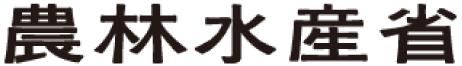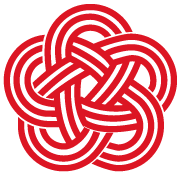
馴れずし(なれずし)

発酵食品
三重県馴れずし(なれずし)
分類(大)
水産
分類(小)
水産発酵食品
主な使用食材
あゆ、米、塩(魚は地域によってさんま、さば、かます、このしろ、たい、あじなど)
※ダウンロード可能な画像を使用する場合は「リンクについて・著作権」をご一読の上、
出典を農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」と明記し、ご利用ください。
なお、画像提供元の記載がある場合は画像提供元も併せてご記載ください。
画像提供元の記載例
【画像提供元の記載がない場合の記載例】
出典:農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」
【画像提供元の記載がある場合の記載例】
出典:農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」
画像提供元:〇〇〇
主な伝承地域
三重県全域
食品概要(特徴・種類)
馴れずしは、樽の中で魚を塩と炊いた米で乳酸発酵させた、独特の匂いと酸味が特徴の保存食。三重県内では各地でさまざまな魚種で馴れずしが作られており、伊勢市ではあゆ、たい、あじ、東紀州ではあゆに加え、さんま、さば、かますなど、中南勢地域(芸濃町)、伊賀地域、北勢地域(桑名市)ではこのしろが用いられている。
熊野灘で捕れるさんまは、産卵を終えて晩秋から初冬にかけて南下してきたもので、漁獲する頃にはさんまの脂肪が落ち、姿もほっそりしてあっさりしているので、丸干しにしても油焼けしにくく、馴れずしやさんま寿司などの日持ちする加工品にも適している。
馴れずしには、1~3か月程度漬け込む「生馴れ」と、滋賀県のふなずしに代表される最低1年、時には2~3年漬け込む「本馴れ」があるが、三重県のものは全て「生馴れ」である。
東紀州地域ではあゆ、さんま、さばなどの魚を12月上旬頃から飯と共に漬け込み、正月に食べることが多い。東紀州地域の家庭では、正月以降1月上旬、2月上旬、3月上旬に約3週間程度漬ける。3月に漬けたものを3月20日前後に口開けしてその年の馴れずしづくりが終わる。
歴史・文化、関連行事
馴れずしは東南あじアの山岳地帯で生まれた魚の貯蔵法が、稲作と共に日本に伝わったものと考えられる。発酵が進むにつれて「馴れる、熟れる」ことから馴れずしと呼ばれている。
元々は魚を長期保存するための加工方法だったため、発酵を促す飯は捨てられていた。しかし、室町時代には発酵期間を短くし飯も魚と共に食べる「生馴れ」が生まれた。この酸味のある飯が、後に今日食べられている「すし」へと発展していった。馴れずしが、すしの先祖と言われる所以である。
製造方法
魚の下処理と塩漬け方法は大体いずれの馴れずしとも変わらない。そして1か月ほど塩漬けした魚を、漬け込みの前日に水で丁寧に洗い塩抜きをおこない、水切りする。
そのあとの方法は使用する魚の種類、漬ける時期、目的、米の炊き方など地域により千差万別である。
馴れずしの漬け方は地域ごとに特徴があり、津市、伊賀市では漬ける際に柚子を使う。伊勢市では炊き上がった飯に麹を混ぜる。桑名市ではしょうがを使用する。飯の扱い方から漬け方、使用する副材料に至るまで各地域の馴れずしごとに独自性がみられる。
保護・継承の取り組み
現在も家庭でつくられており、東紀州地域ではスーパーマーケットでも売られている。その他の地域で神社の熟饌(じゅくせん/神様にお供えする食事の中で調理したものをさす)の場合は祷屋(とうや)組織がしっかり受け継いでいる。神社が無くなっている地域では馴れずし好きの有志が集まって漬けている。保護・継承活動を行う組織がしっかり出来ているところもあるが、地域によっては、好む人の減少、漬ける人の高齢化などにより、消滅の危機に直面している馴れずしもある。
主な食べ方
東紀州ではお正月のおせちの一つや酒の肴として食される。そのまま、または七味唐辛子を入れた醤油につけて食べる。神社の熟撰として作られるものは、神様のお下がりとして、各氏子に配布され、各氏子が家庭で、家族で分けて試食する。