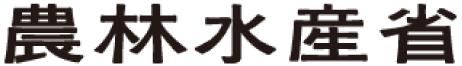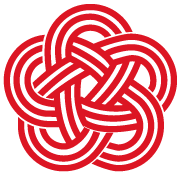
寺納豆(てらなっとう)

発酵食品
京都府寺納豆(てらなっとう)
分類(大)
農産
分類(小)
豆類加工品
主な使用食材
大豆、麹、はったい粉、塩
※ダウンロード可能な画像を使用する場合は「リンクについて・著作権」をご一読の上、
出典を農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」と明記し、ご利用ください。
なお、画像提供元の記載がある場合は画像提供元も併せてご記載ください。
画像提供元の記載例
【画像提供元の記載がない場合の記載例】
出典:農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」
【画像提供元の記載がある場合の記載例】
出典:農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」
画像提供元:〇〇〇
主な伝承地域
京都市、山城地域
食品概要(特徴・種類)
寺納豆は蒸したり煮たりした大豆にはったい粉(大麦または小麦を炒って粉にしたもの)と麹菌をまぶし、塩水に浸けて熟成させた後乾燥させたもの。納豆菌は使用せず麹菌で発酵させる点で味噌やしょう油に似ている。糸を引かず、ぼそぼそとした黒い粒状で、酸味・甘み・うま味が特徴的。色は黒く、発酵と天日干しでアミノ酸が引き出される。中国の豆鼓や愛知の八丁味噌と似た味わい。夏から秋にかけて作られる。
歴史・文化、関連行事
寺納豆は、鎌倉時代に中国から禅僧を通じて伝わった。初めは公家や寺院などで食され、肉や魚をとらない禅寺において貴重なたんぱく質源として重宝され、保存食としても使われた。一休宗純が製法を広めたとされ、当時とほぼ同じ作り方が今も引き継がれている。
製造方法
寺納豆は、蒸したり煮たりした大豆にこうじ菌とはったい粉などを混ぜて発酵させたものを木桶に塩、水と共に入れる。それを毎日ヘラでかき混ぜながら熟成させ、その後天日干しで乾燥させていく。完成までは数か月かかる。
保護・継承の取り組み
現在でも一部の寺において、昔ながらの製法で作られている。また寺の御用達で作る製造業者も、寺の周囲にいくつか現存している。
主な食べ方
ご飯と一緒に食べたり、お茶うけや酒の肴としてそのまま食したりするのをはじめ、料理の調味料として活用されている。日本食はもちろん、西洋料理の隠し味としても使われている。
最近では和菓子をはじめ、チーズケーキ、ドーナツ、マカロンなど洋菓子にも応用されている。