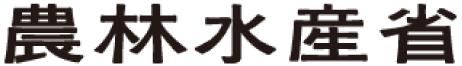乾物
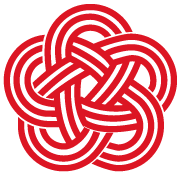

歴史、文化
乾物とは、水産物をそのまま、あるいは内臓やえらを除くなどした後、乾燥させて保存性を高めた加工品で、一般的に「干物」と呼ばれる。水産物は水分が多く、自己消化酵素や細菌の作用により変質・腐敗しやすいが、乾燥させて水分量を減らすことで、その作用が抑制される。
干物の歴史は古く、縄文時代の遺跡から魚や貝を干したと思われる形跡が見つかっているという。奈良時代(710~784年)の正倉院文書にも、神に捧げる貢物「神饌」として記されている。平安時代には「からもの」と呼ばれ、貴族の酒宴の肴(さかな)とされていた様子が『源氏物語』にも登場している。江戸時代に入ると、各藩で産業振興を目的に名産品の製造が奨励されたこともあり、各地を代表する干物がつくられるようになるとともに、庶民が日常的に食べるようになった。
現代では、冷凍、冷蔵、包装などの各種保存技術が発達し、伝統的な干物の技術とこれらの技術を併用する形で、「一夜干し」と呼ばれる低塩分・高水分のやわらかい干物がつくられるようになった。また、乾燥方法も機械化されることで、天候に左右されずに乾燥が可能になり、製造工程の迅速化や乾燥過程における原料成分の変質の抑制が図られるなど、伝統的な乾製品からの変容がみられる。
特徴、種類
乾燥方法には自然乾燥させる「天日干し」と、機械や吸湿物を用いる乾燥法に大別できる。さらに調理後の処理や、塩漬け、煮る、焼くなどの複数の工程を組み合わせて製造される乾製品もあり、種類は多様である。それらの工程を経ることで、素材自身が持つ自己消化酵素を失活させ、付着している細菌の増殖を防ぎ保存性を高めるとともに、乾燥を容易にする効果がある。
また、身欠きにしん、するめ、干しなまこなどのように、乾燥させることで生鮮時の状態とは全く異なった風味・食感を呈するものもある。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 素干し | 原料を水洗したのち乾燥させたもの。するめ、畳いわし、干し海苔のようにそのまま食されるものと、身欠きにしん、棒だら、揉みわかめのように、一度水に戻してから調理素材として利用されるものがある。(田作り(かくたちいわしの素干し)、身欠きにしん、するめ、ふかひれ(さめ類のひれの干物)、くちこ、干し海苔など) |
| 塩干し | 原料を塩漬けしたのち乾燥させたもの。塩漬け中に熟成され独特の風味が醸成される。(うるめ丸干し、あじ開き干し、剥き身だら、いなだ(ぶりの塩干し)、からすみ(ぼら、めなだの卵巣の塩干し)など) |
| 調味干し | 原料を調味したのち乾燥させたもの。(各種みりん干し、いわし桜干し、えいのヒレなど) |
| 煮干し | 原料を煮熟したのち乾燥させたもの。煮干しはだし素材として用いられることが多いが、これは煮熟することで魚自体が持つ自己消化酵素が失活し、うまみ成分が変化せずに保たれることによる。(煮干しいわし、しらす干し、干しえび、干し貝柱、干しあわび、干しなまこなど) |
| 焼干し | 原料を炭火で焼いたのち乾燥させたもの。焼くことで、魚の生臭さが消失し、香味が付与される。(焼きあご、焼干しいわし、焼きあゆ、焼きえびなど) |
| くん製 | 原料を調味したのち、煙でいぶして乾燥させたもの(スモークサーモン、いかのくん製、ほたてのくん製など) |
| 凍乾 | 原料の凍結・融解を繰り返して乾燥させたもの(めんたい、寒天など) |

製造方法
最も簡単な方法は天日乾燥による製造法である。原料をそのままか、あるいは内臓やエラを取り、開いて魚体をよく洗い、天日などで乾燥させる。簡単ではあるが、原料の鮮度、乾燥温度、湿度、時間の調整など技術が必要である。
塩干しは、下処理した原料全体を塩漬けするか、塩分濃度10~20%の塩水に浸す「立て塩」を行ってから乾燥させる。塩分濃度や漬け込む時間は、魚の種類、大きさなどによって異なる。
煮干しは、下処理した原料を塩水または淡水で煮熟したのちに乾燥させたもので、煮熟することで自己消化酵素と付着している細菌を失活させるとともに、タンパク質が熱変成して離水し、乾燥が容易になる効果がある。
焼干しは、下処理した原料を金網に載せて七輪やいろりなどで焼いた後、乾燥させる。

地域との関係性
各地域で、その地域で取れる魚介類を用いた伝統的な干物が伝わっている。今日では全国で食べられるししゃもの干物は、塩漬けしたししゃもを気温10℃以下で天日乾燥させたもので、もともと北海道のアイヌの人たちの保存食であった。富山湾の名産として知られる白えびは素干しにされ、そうめんのだしとしても人気が高い。新潟県村上市の「塩挽き鮭」は、大型の鮭を1週間ほど塩漬けして、丁寧に洗った後に、日本海の寒風に3週間ほどさらして熟成させたものである。

珍味として知られる「くちこ」はなまこの生殖巣を乾燥させたもので、石川県の七尾市、穴水町が主な生産地である。また、珍味として知られる「からすみ」は、ぼらなどの卵巣を塩漬け後に乾燥させたもので、江戸時代に中国から長崎県に伝わったのが最初である。現在も長崎県を中心に生産が行われている。
なお、今日の干物の大半は、腹開きとなっているが、かますやさよりは頭を残して背開きにする習わしがある。これは「小田原開き」と称され、腹を開くことは切腹につながり、頭を除くことは戦で負けることを想起させるなど、当時小田原を中心に勢力を拡大していった武家社会との影響が大きい。
その他、日本人にとって古くから重要な食資源だったのが鯨肉である。鯨の化石や遺跡から、少なくとも縄文時代には鯨肉は食べられていたと考えられる。仏教伝来以降、肉食が表向き禁じられるようになっても、当時、鯨は魚と同類と見なされていたため、鯨肉は貴重なたんぱく源として食べられ続けてきた。江戸時代以降、組織的な捕鯨が行われ、供給量も増えると、庶民の味として全国各地に鯨食文化が根付くことになった。戦後の食糧難の時代には、栄養価の高い安価な食材として庶民の暮らしを支え、「鯨肉の竜田揚げ」は学校給食の定番となった。加工品例としては、千葉県南房総地域の郷土料理で、鯨肉をたれに漬け込んで干した「くじらのたれ」などがある。
参考文献
黒川孝雄、川﨑賢一、田中良治、和田卓、岡弘康、森俊郎、神崎和豊、岩本宗昭、滝口明秀、臼井一茂、藤原健、山澤正勝、白川武志、國武浩美、望月聡、野村明著.日本伝統食品研究会編.『日本の伝統食品事典』朝倉書店,P286~P351